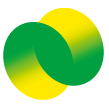出典①:イングランド高等教育財政カウンシル(HEFCE)(英語)
出典②:イングランド高等教育財政カウンシル(HEFCE)(英語)
教育卓越性枠組(Teaching Excellence Framework: TEF)は、ビジネス・イノベーション技能省(Department for Business, Innovation & Skills: BIS)(当時)が2016年5月16日に公表した政策文書(ホワイトペーパー)「Success as a Knowledge Economy: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice」の中で、その具体的な制度案(本サイト2016/6/13投稿記事)が提示され、2016年より段階的に導入されている。
TEFは、質の高い教育を行っている機関の情報を学生に提供して競争市場を形成することにより、評価結果が良い機関には、授業料や教育ローンの上限を物価上昇率に応じて増額できるというインセンティブを提供するものである。
2017年はTEFの導入2年目にあたる。この導入2年目には、全英の大学、カレッジ、代替プロバイダー※1等計299校がTEFへ申請した。
TEFの申請要件
TEFの評価を受けるかどうかは任意であるが、申請の要件として以下の4つが提示されている。
学生支援
- 提供する高等教育が政府より学生財政支援の受給資格を獲得・維持するための特別コースに指定されていること。
高等教育進学の拡大等に係る声明
- 高等教育進学を拡大するという政府の政策を踏まえ、TEF受審を希望する全ての高等教育機関は、締結済のアクセス協定※2(ウェールズ、北アイルランド及びスコットランドはそれに同等のもの)、あるいはイングランドの高等教育機関においては、高等教育進学の拡大あるいは進学に関してあらゆる境遇の学生に対し公平な取組みをすることに関する声明書のいずれかを公表していること。
適切な指標
- TEFの指標に関する3年分のデータを有していること。
- 指標に関するデータが、例えば1、2年分しかない場合はTEFの有効期間もその年数に応じて減じられる。
- 適切な指標に関するデータを有していない高等教育機関は条件付きTEFの称号(Provisional TEF award)が付与される。(有効期限1年)
質に係る評価結果
- TEFの格付けが付与されるためには、高等教育機関はその地域(イングランド・ウェールズ・スコットランド・北アイルランド)の質保証制度における高等教育機関としての要件を満たす必要がある。
- イングランド及び北アイルランドの受審機関には、新たな質保証制度における年次プロバイダーレビュー(Annual Provider Review: APR)(本サイト2017/3/15投稿記事)の評価結果において、「要件をみたしている」、「条件付きで要件を満たしている」及び「保留」の判定であることにより、TEFに申請するための質要件を満たしているとする。なお、質に懸念がある機関については、TEFの称号を失う。
TEF導入2年目の概要
1. 評価の実施主体
- 教育省(Department for Education: DfE)が、HEFCEに委託し、英国高等教育質保証機構(QAA)と共に実施。
- DfEは、TEFの枠組みやTEF付与に係る学費及び教育ローンの値上げ額を決定。
2. 評価対象
- イングランドではTEFは高等教育資格枠組におけるレベル4、5、あるいは6の学部レベル(見習い学位制度含む)のプログラムを対象。
- フルタイム学生及びパートタイム学生に対する教育、遠隔教育、職業訓練及びブレンド教育などあらゆる高等教育形態を対象。
3. 評価枠組
- TEFの評価は、「教育の質」、「学習環境」及び「学生の成果及び学習の効果」の3つの観点から教育の卓越性を判断する。判定は、3つの観点に係るコア指標(core metrics)、コア指標の内訳となるスプリット指標(split metrics)及び追加資料に基づき、教育・学習分野の専門家のほか、学生代表、雇用者の代表等の評価者によって行われる。
| 質の観点 教育及び学習の質の領域 |
教育の質 | 学習環境 | 学生の成果及び学習の効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準 | 教育の質に係る基準 | 学習環境に係る基準 | 学生の成果及び学習の効果に係る基準 | |
| 根拠 | コア指標 | |||
|
|
|
||
| スプリット指標 | ||||
| 追加資料(高等教育機関より提出) | ||||
| 所見 | 優れた点を含め、評定の理由説明 | |||
| 全体の成果 TEFの格付け |
格付けの付与 | |||
4. 受審機関に関わるデータ
- TEFにおける評価者は、受審機関に関わるデータ(Contextual data)を受領する。このデータは、評価者が、当該機関の現況や体制(規模、立地及び学生数等)を理解するためのものであり、コア指標及びスプリット指標の分析にも同様に役立てられるほか、受審機関が実施する特定の取組みを考慮する上でも参照される。
5. 受審機関からの提出物
- 受審機関はコア資料及びスプリット指標に係る取組みに関連し、評価者が審査の際に用いる教育卓越性の根拠資料を提出する。提出物は、それぞれ15ページ以内とする。
- 受審機関からの提出物は、コア指標及びスプリット指標の補足あるいは論拠、背景となるデータの補足、またスプリット指標に基づき、特定の学生集団のパフォーマンスに焦点を充てる目的で用いられる。
6. 評価結果
- 評価結果は、金、銀、銅のいずれかに格付けされ、その評定の理由を簡潔に説明する。
- 受審機関の約30%が金、約50%が銀、約20%が銅の割合を目安として判定が行われる。
- TEFの結果については、HEFCEの高等教育登録簿(the Register of HE Providers)等のウェブページに掲載される。
- TEF導入2年目に付与されたTEFの称号は、原則として3年間有効である。(ただし受審機関が評価に必要な3年間の指標を持っていない場合は、この限りではない)。
7. TEFにおける格付けの定義(TEF Descriptors)
- TEFにおける格付けの定義とは、TEFの基準に照らし金・銀・銅のそれぞれの格付けが付与されるのにふさわしい高等教育機関の特徴を示している。評価者はこの定義を参照して格付けの決定あるいは調整を行う。
- 金・銀・銅の格付けが付与される高等教育機関の特徴はそれぞれ以下のように示されている。
| 金 | あらゆる背景の学生に対し、とりわけ、高レベルの知識や技能を身につけさせるとともに、高い技能を有する職への就職や卒業後の学習の継続に関して、極めて優れた成果等を常に上げている高等教育機関。 |
| 銀 | あらゆる背景の学生に対し、とりわけ、高レベルの知識や技能を身につけさせるとともに、高い技能を有する職への就職や卒業後の学習の継続に関して、優れた成果等を上げている高等教育機関。 |
| 銅 | 多くの学生は良い成果を上げているものの、とりわけ、高レベルの知識や技能を身につけさせるとともに、高い技能を有する職への就職や卒業後の学習の継続に関して、1つないし2つの領域で著しく他機関と比較して下回っている成果を有する高等教育機関。 |
8.TEFにおける評価者及び委員
- 評価は、英国の全域(イングランド、北アイルランド、ウェールズ、スコットランド)から任命されたTEFにおける評価者及び委員が行う。
- TEFにおける評価者は、アカデミアまたは学生より構成され、受審機関からの提出物を評価し、暫定の格付けを行う。
- 委員は、TEFの格付けにおける意思決定機関であり、アカデミア、学生及び雇用者等で構成される。 TEF委員は、評価者としても務めるほか、TEFにおける評価者が決定した格付けに係る暫定結果を調整し最終的な評価を行う。
8. 評価プロセス
- 評価プロセスは、以下のとおり3つのステップに分かれる。
ステップ1(個別評価)
- TEFにおける評価者・委員が、受審機関からの申請書類等について審査を行う。
- 各申請書類審査の際には、最低2人のアカデミア及び1人の学生が対応するように割り当てられる。
ステップ2(暫定の格付けの決定)
- 評価者・委員は、会議を開催し、ステップ1の個別評価の結果をもとに暫定の格付けを決定する。
ステップ3(最終判定)
- 格付けの最終結果を決定するためにTEFの全委員が集う会合が開催される。ボーダー上にあるケースや評価者が判定困難であると判断したもの等についてこの全体会合で判断される。
異議申立て
- 受審機関は、TEFの申請書類の検討事項に重大な手続上の瑕疵がある場合、TEFの判定に関して異議申立てをすることができる。ただし、受審機関は、評価者の学術的判断またはTEFの実施原則に異議を唱えるような異議申立てはできない。
TEF及び新たな質保証制度の関係性
- TEF及び新たな質保証制度は、連動しているものの、異なる役割を担う。TEFは、高等教育機関が学生に良質な経験を提供し、より良い学習成果を上げられるようにすることを目的としている。一方で質保証制度は、学位の品位を保つことにより、英国の学位の価値及び評判を守ることを目的としている。
- 新たな質保証制度における年次プロバイダーレビューの際に収集されたデーターは、TEFの審査においても用いられる。
※1
学位授与機関と連携して高等教育プログラムを提供しているが、公的資金を受給していないプロバイダー。
※2
英国では、2006年度の多様な授業料制度の導入を踏まえ、教育機関が基準額を超えて授業料を設定しようとする場合は、高等教育機会均等局(Office for Fair Access: OFFA)の局長との間でアクセス協定を締結する必要がある。
※3
高等教育統計機構(Higher Education Statistics Agency: HESA)